"The Cold War and American Science"の第3章 [仕事とその周辺]

-------------------
アメリカのトップ大学での軍事研究の歴史の記事で,"The Cold War and American Science"のイントロ全訳を紹介しましたが,第3章の全訳(仮訳)を掲載します.(
MITが慣性誘導などミサイル技術開発に深くコミットしていく様子が活写されています.「デュアルユース」などとカタカナを使うことで軍事研究への敷居を取り払えば,いずれ日本も米国の大学の轍を踏むことになるでしょう.
小見出し
産業界への期待
戦争
ガスタービン研究所
海軍超音速研究所
空力弾性・構造研究所
機器研究所
----------
3.軍事目的の誘導・制御技術
1958年秋,MITの航空工学科主任チャールズ・スターク・ドレーパーは,彼の学科の名前として宇宙時代の到来に先駆けるような新しいものが必要だと考えた.人文社会学部の学部長は,若く優秀な古典学者をその支援に充てた.彼はとても独創的な6つの案を持って来たが,その中にはEuthyphoric(真道飛行科学)工学科やPhoromorphics(無機飛行体構造姿体研究)学科があった.学科長はArchophorology(飛行開始制御科学)学部をドレーパーに推薦したが,「これは君がやろうとしているアイデアに沿うと言うより,ただ,とりあえず面白く思っていることを伝え,またわれわれ人文学の人間が常に工学部を心から応援していることを示そうとしたのです」と言い添えた.
ドレーパーは伝統的な航空宇宙学科の人間であったが,この古典学者の大風呂敷の名称は,ややぎこちないとは言え,ドレーパーの学部の独特のキャラクターをなかなかよくとらえていた.ドレーパーは,1930年代初頭に単一の課程とわずかの航空機装置のガラクタ,それに数名の大学院生で始めたこのインスツルメンテーション・ラボラトリー(機器研究所)を,慣性誘導の研究開発では世界でもトップクラスの研究センターに育て,その過程でMIT本体と並ぶほどの学術帝国を築き上げた.彼が引退する1969年頃には,この研究所の5,400万ドルの年間予算は(リンカーン研究所を除き)MITの他の研究所全部を合わせた額に匹敵した.
ドレーパーは彼の研究所の強大さの源を率直に明かしている.「MITにおける航空工学と宇宙工学は,今もそうであるように,政府資金で実施される委託研究に非常に強く影響されて来た」と,彼は1959年の研究所年報で語っている.彼の説明によると,それらの研究契約は,研究所にとっての唯一の資金や設備の供給源というだけでなく,新しい学問分野を創設することでもあったのである.「委託研究は,航空・宇宙工学における現在の必要性と将来の傾向にマッチした新しい時代のカリキュラムと教育課程を担うべき航空工学部に取って知識と経験の主な源の一つであり続けて来た.」
ドレーパーが詳しく触れなかったのは,委託研究のほとんどが軍からのものであったという事実である.たとえば,1958年にドレーパー自身の研究室は1,290万ドル(海軍からの980万ドルの最大部分はポラリス誘導システム向け)を,空軍から310万ドル(その最大部分はタイタンⅡ型ミサイル誘導システム向け)を受け取っている.海軍超音速研究所は150万ドルの予算規模だが,赤外誘導システムの空気力学的加熱の研究資金を陸軍と海軍から受け取っている.予算60万8,000ドルの空力弾性・航空機構造研究所(ASRL)は,核爆発の航空機とミサイルへの影響研究に特化している.事実,ガスタービン研究所でのジェットエンジン製造者(彼ら自身、主要な防衛契約者)との小規模な契約を除き,1,460万ドルの研究予算の事実上全部が国防総省から来ている.大学院生も同様である.1958年から59年にかけてこの学科に入学した104名のうち59名は,兵器システム,装備機器,推力工学,航空力学の特別コース(しばしば機密の)履修のためMITに派遣された軍の士官たちであった.
軍からの資金とそれに伴う期待とで支配された委託研究プログラムは,不可避的に教育カリキュラムにも同様の影響を及ぼす.その影響はMITに留まらずはるか広範に及んだ.他大学や研究所に比べ教授団の規模がより大きく,より多数の卒業生,産業界とのより密接な結びつき,そして政府の委員会により多数のメンバーを送るなどにより,MITは戦後の航空工学の模範となった.MITの卒業生は,ロングアイランドからロサンゼルスにいたる,契約先でもある主要航空機産業の幹部や技術主任に,陸・海・空軍の上級将校に,そしてMIT自身や他の大学の上級研究者に就職した.彼らは学んだ技術だけでなく,国家安全保障を中心に考えるという特有の世界観をも携えたのである.
産業界への期待
海軍のお陰で,MITは米国における航空工学の研究開発においてその最も初期の段階からの参画を誇ることが出来た.その創始者はボストン海軍工廠の造船技術助手ジェローム・ハンセイカーで,彼は海軍士官たちに航空力学の特別コースを教えるためにMITに派遣されていた.彼は上司に「航空機設計などの学科を作ることは海軍にとって非常に好都合なことなので,この創設プロセスを支援するために軍士官が派遣されるのは適切なことだろう」と説明した.ハンセイカーはその夏を,イギリス,フランス,ドイツの先進的な技術に追いつくことに費やし,イギリスの国立物理学研究所で学んだものをモデルにした風洞を設計しMITに建設した.そのプロジェクトで彼の助手を務めた学生に,のちに自分の名前を社名とする航空機会社を設立するデヴィッド・ダグラスがいた.ハンセイカーが最初に教えた科目は「造船技術者のための航空学」で,最初の学生の全員が,航空学の上級研修のためにMITに派遣された軍の士官たちであった.
ハンセイカーと,彼の教育課程の戦時中の卒業生で,後継者となったエドワード・P・ワーナーのもとで,軍はMITの航空学で中心的な役割を続けながら1920年代に入る.軍は,戦時中と同様にMITの風洞を頻繁に使い続けた.そして学生を送り続け(当時の大学院入学者の約半数),その中に,1924年に修士号を取ったジミー・ドゥーリトルもいた.ワーナーは1926年に,海軍航空部の最初の事務次長に就任するためワシントンに移った.これはMITの教授陣が大学と,軍の高官や顧問との間で行ったり来たりするというやり方の見本となった.彼は,公的には大学を離れている間も教育課程に注目し続け,「次に取るべき方策を決めるために」大学から報告を受け続けた.
戦後の防衛費の削減を受けて,MITはその差額を埋めようとして慈善団体や産業界に期待した.1926年にMITは,民間航空再建の目的で鉱山相続者ダニエル・グッゲンハイムが創設しその息子ハリーが運営するダニエル・グッゲンハイム航空学振興基金に,23万ドルの補助金を申し込んだ.これは,この研究プログラムが,軍用機に求められる完全な性能を追求するという類いのものでなく,信頼性と便宜性の向上を目的とするという約束の上で,MITは資金を得た.MIT学長のサミュエル・ストラットンはグッゲンハイム親子に「われわれは,MITの役割は産業界の設計者,特に民間機の設計・製造者に奉仕することだと考えている」と請け合った.
グッゲンハイムの補助金は,航空工学の年間予算を一挙に3倍化し,10万ドル以上になり,また他の私的資金の呼び水となった.1928年には,ジェネラル・モーターズの社長(MITの卒業生)アルフレッド・スローンは会社の航空部門への投資の増大を計っていたが,グッゲンハイム研究所付属の内燃機関研究所に8万5千ドルを寄付した.少し前にライト航空機会社から移って職員になっていたC.F.テイラーは,その初代の所長になった.
MITは,老朽化した風洞を更新するため,再び産業界に目を向けた.次期学長のカール・コンプトンは1933年に,機械工学科の学科長として,また航空工学コースの主任としてハンセイカーを呼び戻した.カルテク(カリフォルニア工科大学)の,非常に成果を挙げている共同研究プログラムを含む最近の新機軸に対抗するため,ハンセイカーは新型風洞のために23万ドルを調達した.その多くは航空機会社や産業界の幹部たちからのものである.1938年に完成した「ライト兄弟風洞」は, ハンセイカーが予測した通り企業との利用契約だけで元が取れ、最初の2年だけで5万9,000千ドルを稼いだ.
MITは企業からの借りの多くを,よく教育された卒業生を送り込むことで返した.1939年までに学科の全入学者数は,大学院生36名も含めて233名である.ハンセイカーは次のように自慢する.「私たちの卒業生の航空機産業界への影響を見積もることは出来ない.しかしMITの卒業生にカーチス・ライト社,グレン・L・マーチン社,プラット・アンド・ホイットニー社,ヴォークト社,ハミルトン・スタンダード社,ロッキード社,スティアマン社,ダグラス社の技師長や主任技師が,また海軍航空機工場とライト飛行場(空軍)の技術士官が含まれることを記しておくのは意味があるだろう.われわれの若い卒業生は,研究開発のエンジニア,研究者,そしてキーパーソンとして,どこでも卓越している.」
同僚らと共にドレーパーは1930年代に企業的実績においても名声を得た.ドレーパーはテイラーの航空エンジン研究所の研究助手としてキャリアのスタートを切り,内燃機関のノッキングについての測定をしていた.テイラーの弟エドワードとの共同研究が頂点を極めたのは「MITノックメーター」の開発に成功した時である.1934年にドレーパーはインスツルメンテーション・ラボラトリーを創設し,そこで彼と大学院生,助手による小規模なチームは,際立って厳密なやり方で高度計,対気速度計,磁気コンパス,そして他の航空機装備機器の研究に手を延ばした.
ドレーパーの仕事はスペリー・ジャイロスコープ社(以下スペリー)の関心を引いた.この会社は海軍向けのジャイロコンパス,ジャイロ安定器,射撃管制システム,航空機自動制御装置の最大の納入業者であった.1930年代の中頃までに,スペリーは海軍航空部門に新しいマーケットを探していて,またMITや他の大学のエンジニアとの新しい協力関係に目を向けていた.スペリーはドレーパーの早期燃焼インジケータープロジェクトに年5,000ドルを提供したが,これは,ドレーパーの言うところでは「車のジャンク部品置き場から材料を取って来てものを作った」当時、一度に受け取る額としては相当なものであった.スペリーはまた,ドレーパーが海軍向けに並行して開発していた飛行時振動モニターに関する契約もまとめ,独占使用の見返りとして毎年の手数料と5%の特許権使用料をMITに支払うことにした.スペリーの投資はすぐに実を結んだ.「MIT—スペリー振動計」はわずか6ヶ月間で2万ドル分を海軍に売り上げた.
ドレーパーのスペリーとの接触と契約は,彼を一層ジャイロ技術の新しい応用に向かわせたが,これはスペリーのもともとの得意分野であった.年1,500ドルの企業資金で,彼は改良型の傾斜旋回計(バンク・アンド・ターン・インジケーター)を設計,製作した.これは従来のボールベアリングの代わりにバネのサポートをもち、また液体ダンパーを備えたものである.スペリーが営業上の理由でこのアイデアを採用しないことを決めると,ドレーパーは,ラウンド・ヒルにある民間航空局,陸軍航空部と共同でスペリーが開発中だった計器着陸装置にこれを組み込んだ.彼は,パイロットに着陸時に高度の変化をオシロスコープ上の光の点として示すバンク・アンド・ターン・ジャイロスコープを組み上げた.
スペリーは,学生への資金援助と卒業生を受け入れることでもドレーパーの研究所との結びつきをさらに強めた.1930年代の終わりまでに,ドレーパーは航空学プログラムの中に独立した部門を設立し,教授3名,講師2名,技師,装置製作工,機械工の一そろい,それに25名の大学院生を擁した.彼らのほとんどはスペリーとの契約の仕事などに従事した.ドレーパーは彼の研究の成り行きで授業を作って行ったので(「私は教科書で授業をしたことは全くない.その時々,実験室で経験していることから授業を作った.」),彼の商品目的の研究の興味が広がると,それにつれてかれの授業科目も増えていった.例えば彼は1938年に「振動測定」という新しい授業科目を作ったが,これは彼とジョージ・ベントリーによるスペリーと海軍のための研究を直接素材としたものである.ベントリーは飛行時振動モニターのテーマで博士論文を書き,その商業的実用化のためにスペリーに職を得た.ウォルター・マッケイは新型のコンパス解析装置で学位論文を書き,スペリーのジャイロコンパス部門に入った.ウォルター・リグレイの学位論文はスペリーの会社の利害との結びつきが強過ぎたので,彼は詳細の全てを発表することが出来なかった.彼もまた卒業と同時にスペリーに入った.
このように研究,教育,そしてコンサルティングで多忙であったにもかかわらず,ドレーパーはなんとか時間を見つけて自分自身の学位を(1938年に物理学で),また飛行資格も取っている.彼は小型飛行機を個人で買って装置のテストをしたり,また飛行そのものを楽しんだ.同僚は彼の向こう見ずな飛行ぶりが強い印象に残っている.当時の学生たちは,彼がいつも緑の日除け帽と汚い実験着姿で,熱心な助手たちを従えて教室に入って来たのを覚えている.彼の日常のスタイルは,前夜に浮かんだアイデアを形にしていくことに活発に時間を使うというものだ.同僚らは彼が創造的かつとても精力的で,しかも時折アフターファイヴに強いウイスキーを何杯かやるという,相当な酒飲みだったことを覚えている.(彼の机上時計に仕掛けられたスマートな回路のおかげで)簡単に5時が表示されるようになっていた.
戦争
戦争と,特に日本空軍の憂慮すべき強化はドレーパーの研究に緊急性と方向性とを与えた.スペリーは傾斜旋回計を計算照準器(自動的に適切な距離で標的の前方に狙いをつける)に転用するというドレーパーのアイデアを支援し,その後これを対空砲の照準器として,当時太平洋で大きな損害を被っていた英海軍省に売却した.米海軍は,最新の自動制御の理論と実際を電子技術エンジニアのゴードン・ブラウンに学ぶためにMITに派遣されていた若手将校グループからこの情報を知った.ブラウンは火器制御の研究で別にスペリーと研究契約を結んでいた.将校たちはドレーパーのコースも受講し,そのうち2人はジャイロ制御の高射砲への応用で秘密研究の学位論文を書いた.ドレーパーの研究に感銘を受け,彼らは海軍兵器局の正式試用に便宜を図った.この試用はMark 14と呼ばれる対空砲照準器2,500セットのスペリーへの製造契約につながった.同時に海軍はドレーパーに,ジャイロ照準器の技術研究をさらに進めるための機器開発秘密研究所(CIDL)をMITに設立する契約を与えた.
基本的な概念を確立したCIDLは,望遠鏡,起爆タイミングコンピュータ,無視界射撃のための測距レーダーを装備したより大型で射程も長い大型のものに向かった.ドレーパーは当時を思い出して次のように述べている.「われわれは何でもやった.テーマを考え出し,数学をやり,設計をやった.部品を作り,部品を組み立て,そしてそれをテストした.そういうわけでわれわれは設計,エンジニアリング,そして実験のすべてをやる小さな会社だった.われわれは,何らかの機能を持つ部品を製品化するまで何でもやった.その場合われわれは道具に仕上げようとしている会社であればどこにでも情報を提供した」.ドレーパーの技師たちはスペリーの技師たちに照準器の組み立て方を教え—ある時点では会社は50人の技術職員が研究所に派遣されていた—軍の士官たちにはその配備の仕方を教えた.スペリーは最終的に85,000 基余りのMark 14を製造し,特許所有者のMITに40万ドル,共同発明者のドレーパーに1万500ドルの特許収入をもたらした.終戦までにCIDLは100人のスタッフをかかえ,百万ドル台の年間予算を持ち,陸軍航空隊,海軍,スペリー,そしてACスパークプラグ社との契約を取った.
戦時研究は他のMITの航空工学研究室も巻き込んだ.ジョン・マーカムはライト兄弟風洞を1日2シフト,週7日稼働させ,マーチン,グラマン,ロッキードその他の航空機製造会社の新規にデザインされた飛行機のモデルをテストした.テイラー・ブラザーズはスローン・ラボラトリーに航空燃料の研究をさせた.マンフレート・ラウシャーは陸軍航空隊と海軍の資金を得て,高速での主翼,補助翼,尾翼の振動の研究のための特製の「フラッター風洞」を設計,建造し,そのマシンで数千もの試験を指導した.その中にはヴォート社のSB2Uやグラマン社のヘルキャット急速降下爆撃機も含まれる.
ガスタービン研究所
これらの共同研究の新しいパターンをMITの強みにする方策を求めて,ハンセーカーが委員長を務める教員による委員会は,ガスタービン研究所の設立を大学当局に認めさせ,他の財源が見つかるまでの当初費用2万4,000ドルの手当をした.ガスタービンエンジンは,戦前は将来性のあるアイデアというに過ぎなかったが,ドイツ,イギリス,そして米国での大規模な戦時研究の中で革命的な技術として現れ,一流の大学プログラムならばとても無視できないものだった.
1944年春,カール・コンプトンは期待される協力企業家との話し合いを開始した.その中には(アリソン部局を通じて)所有する会社がすでに軍用機エンジンの大手供給者で,新しい展開に遅れないよう躍起になっていたアルフレッド・スローンも含まれる.スローンは,スローン研究所に隣接する戦時の燃料研究所を,ガスタービン研究所(GTL)を容れるためにMITが海軍から買い取るための資金4万ドルを寄付した.スローンはGMとの独占的な研究契約を望んだ.コンプトンは,たぶん1920年代末の過度に制約的な民間との契約の悪い記憶から,彼にそうしないよう次のように説得した.「私はMITが実験室のドアをそこの学生に対して閉じるような政策をとっていいものかどうか,もしくは教授たちのあるグループを — その多くはコンサルタント契約を他の会社から変更していたが — 一つの会社の利益に奉仕させるような政策を取っていいものかどうか,いくらか疑問に思った.」その代わり,学科の視察委員会は研究所のための必要額の残りを航空機エンジン製造業者のコンソーシアムから調達した.ハンセイカーは次のように言って売り込みを図った.「アメリカの航空機エンジンのメーカーはビジネスの脅威に面している.彼らは英国で作られたものやGE,ウエスティングハウス(ターボジェットエンジンの戦時の2大契約企業)がこの国でやったことのコピーをしていたのでは主導権を握ることはできない.私の意見では,彼らは,新しい技術の基本知識をベースにして,優れた設計能力を生かし,先進的な発電所を作ることが出来る.そのような基本的知識を使いこなすためには,彼らは専門的な技術に秀でた若いエンジニアを獲得しなければならず,また研究を通じて自らの応用目的に関する重要な知識も習得しなければならない.提案されているMITのガスタービン研究所はそのような人材と知識とを提供することが出来る.」カーチス・ライト,GE,ウェスティングハウス,ユナイテッド・エアクラフト(プラット&ホイットニー)はそれぞれ12万5,000ドルを,またジェネラル・マシナリー・コーポレーションが2万5,000ドルを寄付した.
ガスタービン研究所(GTL)はエドワード・テイラーを所長に1947にオープンした.GE,ウェスティングハウス,カーチス・ライト,そして遅れてアリソンの各社は、研究所報告、コンサルティング、そしてスポンサーへの報告後1年間は成果の発表をひかえるとの「紳士協定」を見返りとして、それぞれ年1万ドルの運営資金を拠出した.この研究所は急速に成長し,全米トップクラスの研究センターとなり,大きさで2位,名声でこれを凌ぐのは教育義務を持たないバッファローにある学外施設のコーネル大学航空研究所だけであった.最初の10年間にGTLのスタッフは249本の論文・技術レポートを発表し,134名の学生を教育した.うち93名は修士課程,17名は博士課程の学生である.
資金提供者がいくら善意であっても,軍関係の契約は余りにも受けやすくまた余りにも資金潤沢であることにテイラーは気付いた.スタートの時点で研究所は相当な規模の防衛関連プロジェクトにかかり,それには超音速ディフューザおよび超音速圧縮機の研究も含まれる.朝鮮戦争で防衛関連契約が急速に増大し,GTLの年間予算の約40%まで占めるようになった.いずれにせよ軍のガスタービン技術への強い関心は研究所の民生向けの研究を完全に圧倒した.当初テイラーは自動車,鉄道,造船,民間航空からの民生目的での強い支援を予想していたが,実際に資金を出した会社はもっぱら軍用のターボジェットエンジンを製造しているものばかりだった.テイラーは「陸軍と海軍,そして産業界も,ある特定の分野の理解を深めることを目的としたプロジェクトではなく,当面の目標に直結するプロジェクトにしか普通は興味を持たない」と述べている.戦後における陸軍,海軍とその契約企業にとっての当面の目標とは,軍用機のための高性能タービンを供給することであった.
海軍超音速研究所
第二次大戦が終わって数ヶ月後,海軍武器局はMITと巨額契約をむすんだが,それは「ジェット推進で,レーダー誘導式,超音速,艦船上から発射可能な,一つあるいは複数のタイプの対空ミサイル開発に必要なあらゆる科学的・技術的な活動を含む包括的な研究開発プログラム」というものである.プロジェクト・メテオの暗号名を付けられ,5つの学科と6つの研究所にまたがり,50名の教授陣,さらに下請け契約としてベル・エアクラフトのミサイル研究,ユナイテッド・エアクラフトのラムジェット研究,ベンディックス社の制御システム研究が含まれる.
超音速でのミサイルの安定性,制御,操縦性能を評価するため,MITの航空工学エンジニアは超音速風洞での試験データを必要とした.不運にもその唯一のものはNACAエイムズ研究センターの新設の風洞のみで,はるか遠方にあり,しかもその研究所自身のトップ・シークレットのミサイルと航空機研究のため全部ふさがっていた.1,000万ドルのプログラムを出来るだけ早く前に進めるべきとの決意から,海軍は,MITの首脳からもなにがしか説得を受けて,これと同等の超音速風洞をMITに建設することに同意した.
海軍の超音速風洞が総費用260万ドルで完成した1949年12月までに,他の誘導ミサイル研究を優先するためメテオ計画の予算が3分の1だけ削減され,MITは最新技術の風洞と60名のスタッフをかかえたまま何も出来なくなった.ジョン・マーカムは,「超音速の戦闘機,爆撃機,ミサイル開発のものすごい努力が現在行われていること」が意味することを認識して,彼の施設を海軍超音速研究所(NSL)と改称し,すべての契約組織のメンバーに開放した.空軍とその契約企業はこの風洞の新しくまた即時に需要の見込めるマーケットであった.1953年だけでNSLは研究・試験契約としてライト航空開発センターから22万3,185ドル,ボーイング,ヒューズ,プラット&ホイットニー,マクダネルから24万3,250ドルを獲得し,これはメテオ計画のピーク時の契約額をかなり上回った.NSLは1955年に2万ドルの「利益」を上げ,翌年にはこれが35万ドルに拡大した.空軍の関心はNSLの注目点を,ミサイルの空気力学的加熱やノーズコーンの形状,それに超音速でのミサイルや爆弾の運搬と投下という秘密研究の方向へと一層向かわせた.またNSLは,これらに関連する風洞実験を,ボーイング,コンベアー,ヒューズ,マクダネル,ノース・アメリカンその他の航空宇宙産業の契約社のために,新型の航空機(例えばB-58)とミサイル(例えばBOMARC)に対しても稼働させた.その単一テーマで最大規模の研究プログラムは赤外追尾システムへの空気力学的加熱効果の評価に関するもので,空軍と海軍から年間予算90万ドルの支援を受けた.NSLは赤外追尾システムの超高速・高温での性能を向上させるための理論と応用の両面の研究をおこない,サイドワインダーとスパローの二種のミサイルの作動テストのため最初の風洞実験をおこなった.1956年にNSLは赤外追尾システムに関する全米カンファレンスを主催し,また機体の空気力学的加熱に関する夏の学校を共催し,これには企業や政府機関から100人が参加した.
MIT学長のジェームス・キリアンは,この貢献によってNSLは「国家安全保障の決定的に重要な」研究だけでなく「この新しい分野を学ぶ大学院生に刺激的な研究の機会」を提供するだろう,と予言した.NSLは秘密研究プログラムに関わるものでさえ積極的に大学院生や学部学生を募集した.募集広告には「非常勤職または学位取得の素晴らしい機会に興味がありますか? MITの海軍超音速研究所を見逃さないで下さい」とある.その広告はMITの現在の研究課題として「ミサイル誘導システムにおける空気力学的,熱力学的課題」,「高高度ロケットおよびミサイルの弾道予測,ヒーティング,および性能」,「際立った超音速形状の空気力学的設計,試験および評価」,「セキュリティ制限のため書くことができない,上記に関する他の多くの諸課題または諸側面」を挙げている.
マーカムは,国の防衛への最も重要な貢献がいちばん出来そうなのは,ここで学び,研究した院生や元スタッフで航空業界に就職した者たちであると考えていた.彼らは超音速空気力学の,赤外追尾の,そして他の重要技術の専門知識を携えている.常時NSLには12ないし15名の院生が在籍しており,おそらく学部生はその2倍はいただろうし,上級の学位を目指してパートタイムで研究に従事する技術者スタッフもいた.彼らの研究内容は一般的には秘密ではなかったが,委託研究プログラムに大きく貢献した.例えば,秘密ではない拡散冷却の研究は,マーカムの説明では「長距離高速ミサイルでの応用に途方もないくらい関わりがある」.ジャドソン・バロンの博士論文「高速における物質輸送冷却に関わる2成分混合境界層」は,超音速でのミサイルの空気力学的加熱に関する研究所での仕事の直接の産物であり,超音速でのミサイルの激しい加熱を抑制する方法に関する空軍の巨額の研究契約につながった.バロンはのちに学科に助教授として就職した.
空力弾性・構造研究所
空力弾性・構造研究所(ASL)では,原爆と戦略爆撃機という戦争を勝利に導いた兵器が研究所の将来の方向性を決め,それはもはや後戻りできないほどの変化であった.レイモンド・ビスプリングホフは,空軍と海軍航空事務局(1946年にMITに来るまで彼はここで働いていた)の資金を得て,ASLを核兵器の空気力学的効果のシミュレーションと評価のための世界的なセンターに作り上げた.戦略爆撃機が破壊されずにどれだけ原子爆弾の爆発の近くを飛べるかを研究するため,ビスプリングホフと彼の同僚らは98フィートの長さの「ショック・チューブ」という非常に強力な風洞を設計・製造した.原爆の規模の爆風(20トンまでの力)をスケール・モデルに加えることが可能で,衝撃の大きさは干渉計,天秤,そして高速カメラで測定される.ショック・チューブは単一のものとしては研究所の最大の研究プログラムになり,10名のスタッフ,年間予算は68万5,700ドルであった.スタッフメンバーは,空軍と海軍航空事務局のために「航空機体への原爆の効果」についての機密の技術レポートを数十本書き,また1951年のロス・アラモスとエニウェトク環礁での原爆実験の指導さえも行った.のちに彼らはこの種の研究を弾道ミサイルにまで拡張した.
軍用機の速度と機能の向上は空力弾性学と機体構造学研究の従来の課題
もまた再定義した.超音速でのフラッター現象を評価するため,研究所はライト兄弟風洞に可変マッハ数超音速実験セクションを建設した.助教授のホルト・アシュレイやロバート・ハフマンでさえ空軍や海軍航空事務局から24万737ドルの研究契約をもらった.ビスプリングホフは3つの追加契約(「機体構造への衝撃と打撃」,「航空機設計基準」,「突風研究」)の予算37万4,500ドルの研究を指導した.金属疲労のような従来からの課題さえも見直され,民間航空向けの低ストレス・高サイクル疲労ではなく,軍用機向けの高ストレス・低サイクル疲労の問題が急速に関心の的となった.1958年までに,この研究所は6名の教授,20名の院生,42名の補助職員を擁し,経常的な年間予算60万ドルを受け取るが,その全ては国防総省とその契約企業からのものである.
研究所は契約研究が教育に役立っていることをことさら自慢していた.ビスプリングホフは「空力弾性学と構造学コースの優れた内容は,これらの授業を契約研究プログラムの指導者が担当していることによっている」と述べた.実際,研究所が空力弾性学の最新の分野を事実上作り上げた.そのプログラムは年に少なくとも10名の院生を送り出し,その全員が契約研究に負っている.所属の教授たちは空力弾性学のユニークな一連の授業を創設し,それには大学院と学部レベル双方の実験科目も含まれる.適当な教科書がなかったので,ビスプリングホフとアシュレイは自ら「空力弾性学」というテキストを書いた.彼らはこれを「航空機産業界のための教科書兼基礎的参考書」と位置づけた.この本は広く使われる標準的な教科書になった.
研究と同様,教育も軍事航空技術の進歩に密接に追随した.アシュレイと彼の同僚らは1952年までに,「高速の飛行機やミサイルを開発している政府関係研究所や民間企業,またわれわれの研究所のある部門」の職員はみな,空気力学のより進んだ教育を必要とするだろうと確信して,熱効果,波動と衝撃(ショック・チューブについての一節を含む),非定常流,極超音速空気力学,超空気力学の授業を含む新しいカリキュラムを開発した.アシュレイは1957年に「誘導ミサイルの力学と空気力学」という実験コースを開設したが,それが強い関心を集めたため次年度からも常設コースとして継続した.学科は空軍の士官向けに衝撃及び振動をテーマとする特別コースを作ったが,これは後に「ロケット,誘導ミサイルおよび投射体」という空軍,海軍の士官限定の公開コースとなった.次いで,「ロケットとミサイルに対する関心の高まりに応えて」,学科は「空気流体力学,空気力学,航空機安定性と制御のような学部学生向けの授業を,航空機の視点だけでなくミサイルの諸問題についての考慮も含む」ように改訂した.ミサイルを扱う1957年度の選択科目を履修した4年生は,機体とエンジンを備え,空気力学的特性と制御系を含めて,地対空迎撃ミサイルの設計をすることになった.ビスプリングホフは学科への視察委員会に対して,委託研究の教育への寄与についての彼の意見を述べて,それが学生への資金援助になりまた研究所がおそらく自前では買えない数百万ドルの装置類を提供しているというだけでなく,おそらくもっと重要なこととして,挑戦的な研究上の課題や「卒業生にとって有益な航空機産業界や政府機関との接触」も提供していると指摘した.
産業界との連携プログラムに対する研究所の積極的な支援により,宇宙航空産業への扉は常に開かれていた.空力弾性学と機体構造学に関する毎年春のシンポジウムは,教授陣の講演,学生の研究発表,そしてショック・チューブや他の研究施設のツアーなど,ラボラトリーの研究成果の展示場となった.またASLは産業界向けにミサイルと衛星の空気力学に関するサマー・スクールも開設した.これは毎年100名以上の参加者を集め,講義ノートは印刷されてより広い範囲の読み手に配布された.教授たちは主要な宇宙航空産業の会社のコンサルタントを続けた.アシュレイは1956年の夏はコンベア社の構造力学グループと7週間を共にした.ロッキードから1952年にMITの航空工学科に来たポール・スタンドルフは10年後にサバティカルのあいだ会社に戻った.学科長は「産業界での彼の経験は学科の工学の授業に現場での実践から来る最も望ましい雰囲気をもたらす」と記している.
研究所の研究技師たちは,その多くはMITの卒業生であるが労働市場に入る前のなにがしかの経験を求めてその職にあったが,研究所の最新技術をマーティン,ダグラス,ノース・アメリカン,ボーイング,コンヴェアーその他の航空機大手企業に頻繁に流し続けた.ビスプリングホフは,卒業後の教育の成果を提供することは研究所の重要な任務であると感じていた.彼は次のように書いている.「技術職や他の研究補助職員は無期雇用だが,研究スタッフのメンバーはその地位をMITの卒業後の教育期間であると考えて欲しい.これは授業も単位もない無形の教育プロセスだが,われわれが行っている最も重要な教育機能であるということが分かった.」数人のスタッフメンバーはみずから事業を起こした.一人は1952年に原爆の爆風研究のアライド・リサーチ社を,別の2人は電子「シェイカー」や他の空気力学試験装置を製造するカリダイン社を設立した.
ベトナム戦争が激しくなり戦闘ヘリコプターへの注目が高まると,研究所もその経験と専門知識をこの新しい挑戦へと振り向けた.研究所は再び,これらの兵器開発を推進した軍の諮問委員会(研究者のトップが陸軍航空隊の科学諮問委員会の議長を務めた)と,それらを製造した契約企業の双方と密接なつながりを持った.予想されるとおり,研究所の発表論文と学位論文は当時の軍の主要な関心事を反映し続けた.
機器研究所(インスツルメンテーション・ラボラトリー)
ドレーパーの教え子たちは,戦後,空軍と海軍が戦略爆撃機と弾道ミサイルに関心を移す中で,機器研究所を最先端の位置に保ち続けた.その標的はソ連の領土深い所であるため,従来のレーダーや有視界飛行・誘導システムよりも優れた技術が求められた.ドレーパーは代替案として慣性誘導システムを考えていた.精巧なジャイロスコープと加速度計を使うことで,そのようなシステムは,少なくとも理論上は,発射点から標的までの間の自分の姿勢,加速度,重力の変化を完全に測定でき,したがっていかなる種類の外部からの指令や修正なしにミサイルを誘導できる.ドレーパーはこれを好んで推測航法(dead reckoning)の先進タイプと呼んだ.その大きな利点は妨害電波に強いことだが,最も明白な問題点は,地球を半周しても標的に命中させるほどの正確さを持つジャイロスコープや加速度計を爆撃機やミサイルに積み込めるほど小型にするのは出来そうにないということだった.空軍科学諮問委員会の誘導・制御技術パネルの指導的メンバーであったジョージ・ガモフを含めほとんどの専門家は慣性誘導はどうしようもなく非現実的と見ていた.
ライト飛行場の陸軍航空隊武器研究所の所長,レイトン・デイヴィスはもっと詳しく調べようと思った.彼は若手士官の時にドレーパーの射撃制御の授業を取っていて,その後も密接に連絡を取り合い,第二次大戦の終わりの数年間,戦闘爆撃機のジャイロによる射撃制御システム研究に武器研究所からドレーパーが10万ドルの契約を取るのを助けた.A-1照準器は朝鮮戦争まで完成し実戦に使われることはなかったが,デイヴィスはドレーパーと彼の研究室に大きな信頼を持つようになった.日本が降伏したほんの数週間後,デイヴィスは,戦争が終息し始めた頃にドレーパーと議論していた慣性誘導の原理に基づく「恒星爆撃システム」の委託研究を機器研究所に授与した.「リー(レイトンの愛称)と私はウイスキーのボトルからそれを取り出した」とドレーパーは後によくジョークを飛ばした.その時でさえも彼らは単により良い爆撃照準器より以上のものを思い描いていて,次のように述べている.「恒星爆撃システムはもともとジェット機の爆撃照準器として設計されたが,最終的には誘導ミサイルに使ってこれを自動化するという可能性も排除されるべきではない.」
空軍は当初の慣性航法システムの研究段階の契約を,設計の一連の契約として続けた.FEBE(ポイボス,太陽)は,後の基準からすればかさばり精度も低かったが(4,000ポンドで,4時間の飛行で10マイルの誤差),専門家の予測に反して航空機が慣性誘導だけで首尾よく航行できることを証明した.SPIRE(空間慣性基準装置,SPace Inertial Reference Equipment)が恒星追跡による補助装置を不要にし2,800ポンドに軽量化,さらに精度を12時間飛行で10マイルまで向上させた.懐疑論者を打ち負かすべく,ドレーパーは1953年2月8日,SPIREを装備したB-29をマサチューセッツ州レキシントンのハンスコム飛行場からロサンゼルスに飛ばせて,それで軍用ナビゲーションシステムの極秘会合に出席したが,彼の「標的」を12時間のフライトで9マイル以内に外しただけだった.その半分の重量の新型SPIREは1957年に同じコースを飛んで2マイル以下の誤差であった.翌年にはエリック・セヴァレイド記者,ドレーパー,それに6人の研究所の技術者を乗せて,秘密の目的地に向けての全国横断飛行がテレビ中継され,ニュースとなった.
キリアン委員会は機器研究所を弾道ミサイルのビジネスに向かわせた.高まるソ連の脅威に対するアメリカの脆弱性を評価・検討するために1954年にアイゼンハワー大統領によって設立され,MIT学長が議長となった委員会は,中距離および大陸間弾道ミサイルの開発と配備を国家的最優先事項と決定した.政権の最上部のゴーサインのもと,バーナード・シュリーバー将軍率いる空軍西部研究開発部門において,空軍はミサイル競争での優位を強固にするべく意欲的に活動を始めた.
まだ多くの専門家が慣性誘導はあまりにも実験的であり重量が過大だと思っていたが,少なくとも一人,空軍西部研究開発部門の専任の誘導技術の専門家で,ドレーパーの卒業生(軍士官身分で入学)であるB・ポール・ブレイジンゲームというの強固な擁護者がいた.ブレイジンゲームは,「アトラス」(アメリカ初のICBM)に搭載する,無線システムのバックアップとしての誘導装置と,また新型中距離ミサイル「ソー」の最初のシステムのための研究開発を機器研究所に委託するよう彼の上官を説得した.A-1爆撃照準器の製造者であるジェネラル・モーターズのACスパークプラグ部門がこの両者の下請け契約を取った.主にソーでの高性能ぶりが買われて,1959年に機器研究所は初めて100パーセント慣性誘導となる空軍のICBM「タイタンⅡ」の誘導装置の契約を取った.慣性装置の本体をACスパークプラグが,誘導制御用コンピュータをIBMが下請け契約を取った.スプートニク・ショック後のミサイル競争の時代(1957-63)には,空軍は弾道ミサイル誘導システムの開発研究に年900万ドルを機器研究所につぎ込んだ.
キリアン委員会は,核の3本柱のうちの海上の核を承認し,海軍の野望もまた等しく支援した.従来型の地上配備の兵器が間もなく旧式になってしまうことを恐れ,海軍はすでに機器研究所との戦後の射撃管制研究の契約を縮小し始めており,潜水艦の慣性航法装置(SINS)のような新しい構想に傾いていた.SPIREと同様に自己完結型の航法システムを目指していて,短時間に発揮される精度よりも長時間の安定性,信頼性に重点を置いていたが,SINSには精確な位置情報という戦略型潜水艦に特別に要求される性能を期待していた.1959年までSINSという名称そのものも極秘とされていた.
「艦船から中距離にある戦略目標まで妨害に強く全天候の能力を持つ」との触れ込みのポラリス・ミサイルは機器研究所におあつらえ向きの仕事と思われた.まさに適任の男(機器研究所の卒業生サミュエル・フォスター)が最適の場所(海軍特殊プロジェクト本部)にいたため,契約がまとまった.研究所はポラリスの誘導システムの契約を1956年の末頃に取った.1960年に最初に核ミサイル原潜に搭載された,MITが設計しジェネラル・エレクトリックが建造したマーク1誘導システムはわずか225ポンド(102kg)で,初期の航空機向けのシステムのものより一桁以上軽い.後継の,ポラリスA3大陸間弾道ミサイル用のマーク2はさらに精度が向上し,しかも大きさ,重量ともに3分の1になった.ポラリスは「ゆりかごから墓場まで」のシステム・エンジニアリングでこの研究所の名声を不動のものとし,1960年代初期のピーク時には年間およそ800万ドルの収入をもたらした.
ポラリスとタイタンの開発は,規模はこれより小さく概してより基礎的な,進んだ慣性航法装置と関連部品の研究プログラムと併せて,研究所の契約額を年2,080万ドルに増やし,スタッフも,共同開発を進めている企業から配属された200名余の技術者も含めて1,275名を数えるようになった.機器研究所は形式的には航空工学科の一部門に過ぎないのだが,学科の他の研究所全部を合わせたものよりすでに20倍も大きくなっていて,リンカーンと比べられるほどで,またさらに拡大していた.
研究所は1961年にアポロ計画のナビゲーション・誘導システムの開発契約を取った.この時も,古いコネ[NASA長官ジェームス・ウェッブと副長官ロバート・シーマンス]がモノを言った.ウェッブは戦時にはスペリーの最高幹部で,シーマンスは機器研究所で博士論文(迎撃機のための諸自動追尾システムの比較)を仕上げ,その後そこでA-1爆撃照準器の開発に従事,そしてRCAのミサイル・エレクトロニクス部門に移った.NASAの契約額は初年度は440万ドル,翌年1,280万ドル,そして1969年のピーク時は2,590万ドルに達した.常に新しい挑戦への姿勢を持つドレーパーは月探査ミッションにもボランティアとして応募した.彼はシーマンスに,「私はテストパイロットとしては限界があることは理解しているが,科学者・技術者としての私の能力は乗組員として考慮するに値すると思う」と述べた.彼は月に行くことはなかったが,彼の誘導システムは別の人がそれをやるのを保証した.
アポロ関係の契約が甚だしく大きくなったため研究所の軍事と非軍事とのあいだの業務のバランスが劇的に変化し,1961年には事実上すべて軍事関連であったのが1965年までには半々になったが,軍事プログラムの大きさやその影響は減らなかった.空軍の弾道ミサイルと衛星の誘導システムの研究と,海軍のポセイドン・ミサイルと最新型の慣性航法装置の研究で,会計簿の軍事サイドは1968年には2,950万ドルに膨らんだ.
ドレーパーは,機器研究所の財政力の重みだけで学部とMITの中で相当な影響力を持った.彼は,研究所と学科の双方の長として会計簿を自分の目的に合うように操作した.彼は次のように回想している.「私は決して彼ら(MITの理事たち)と予算のことで争わなかった.なぜなら私は彼らに,必要な金額を私に与えるように出来たし,それで私の研究所には十分なお金があり,またどのみち,一筆の書類で自分の望むようにものごとを決められた.」
ドレーパーが何よりも望んだのは研究所が教育機能を持つことであった.ある同僚がその取り組みについて次のように述べている.「ドレーパーにとって教育と研究のあいだの対立というものは全く存在しなかった.これらの二つは一体不可分のものだ.また彼は教育のプロセスが正式かインフォーマルかの区別を気にしないこともしばしばった.ドレーパーにあっては教育とは目を覚ましている時間ずっと行われるもので,意識的であれ無意識的であれ,研究室で,食堂で,実験室で,セミナーで,あるいは講義室で.技術職員や同僚,学部学生との,研究所に派遣された海軍士官との,また誰彼なく議論し学ぼうとする人々との会話で.ドレーパーにとって研究所のすべてが工学教育に不可欠のものであった.それを通して彼は理論に明白な現実性を付与することができ,その重要性も認識できる.」ドレーパーは,委託研究が彼の学生に現実世界の経験と責任意識を提供し,それらが本物の工学教育にとって不可欠のものと考えていた.学生たちは「彼らが私に教務委員会に合格するための論文を渡すとき,単に私を喜ばせようとしていたのではない.学生が作った装置が鳥に付けられ,もしそれがうまく行かなかったとき,なぜ動かなかったかを他の人と同様に,彼らもその理由を知る.」
機器研究所はその資金と同様,学生もまた主に軍から供給された.一般人1名に対し軍の士官が7~8名という状態が相当の期間あり,実質的に軍以外の学生の入学が制限された.1950年代の終わり頃になると,軍の士官[概ね年30ないし40名で,そのほとんどが誘導制御の課程]が学科の院生の約半数を占めた.軍人の学生の増大に対応するため,1952年に学科はドレーパーの弟子のウオルター・リグレイのもとに,独立の「兵器システム工学課程」を創設した.この課程のカリキュラムには,通常の学部が定める内容基準以外に,射撃管制,レーダーシステム,兵器構造学,ロケット・誘導ミサイル・発射体に関する設計特論の,授業と実験の機密の科目が含まれた.どの年度も学生の半数が「兵器システム工学課程」を履修した.
ドレーパーと彼の同僚は,慣性誘導の研究・開発に従事する軍の士官たちと定期的に会い,研究ノートを見せ合い学位論文のテーマについて議論した.カリフォルニア州モントレーの海軍大学院大学での射撃管制の講義の後MITに戻ったドレーパーは海軍の上級士官に次のように報告している.「リー艦長,スミス司令官,それに海軍大学院大学教授陣のいろんなメンバーと兵器システム課程について数時間議論した.MITでのわれわれの大学院教育を海軍士官に必要な教育内容にうまく合わせる最良の方法に関する多くの提案について議論された.」空軍の司令官はこの課程は比類なく有益だと考えて次のように述べている.「ドレーパー博士によって指導されるMITの兵器システム工学課程はわれわれに取って非常に有益である.それは学生とスタッフが,SPIREやリンカーンのような空軍の現在の研究開発プロジェクトと密接に連携しているからである. MITの士官の教育プログラムのような環境を提供する機関は米国では他に存在しない.」この課程は1958年までに118名の空軍士官の卒業生を送り出したが,この数は他の航空工学科の教育課程全部を合わせたものより多い.卒業生の9割が引き続き軍事関連の研究開発に残った.
研究所は前々から,機密研究と機密学位論文を軍と共同で仕事をするためのコストの一部と考えていた.ある航空工学の教授は「機密プロジェクトと一般の研究の両方が機器研究所の教育面に貢献するということを認識するのはやや逆説的だ」と述べた.何人かの学生たちは機密研究プロジェクトの課題で公開の学位論文を書き,他方別の学生たちは公開の学位論文を書いたが,最終的には非公開の論文になった.フィリップ・ラップは,ライト飛行場武器研究所との慣性誘導研究委託のサポートで1951年に弾道ミサイル誘導の理論に関する公開の修士論文を完成させた.彼が博士論文を1955年に完成させるまでに,彼の論文も含め弾道ミサイル誘導についてのすべての研究が機密指定された.機密保持と学生の論文完成とを両立させるため,ドレーパーは1956年に「学位論文機密担当」という役職にリグレイを充て,この職は1960年代の終わりまで維持された.
委託研究が航空工学のカリキュラムに対してどのような意味を持つかということについて,ドレーパーと彼のスタッフに誰も意見する必要はなかった.リグレイは次のように説明する.「研究所の様々なプロジェクトの成果は,数年間は教科書には出て来ない新しい技術的情報を含んでいる.そのような情報は教授の大学院コースの講義ノートとしてまず大学内部で共有される.これらの講義ノートは整えられて書籍になり,非常に短時間で新規の教材として学部学生のカリキュラムで使われる.このパターンは機器研究所の傑出した到達点であった.」
皮肉にも,研究所の最も重要な教科書類の一つはもう少しで出版されずに終わるところだった.ドレーパーは慣性誘導の理論と実際についての最近の発展の総合的な報告書を作ることを長い間望んでいた.ドレーパーによると,それは「研究成果のうち公開されている部分について書かれたものがほとんどないため,その分野の専門家にほとんど知られず,また入手できない」ためであった.彼は,空軍が3巻ものの教科書を作る資金を出してくれるものと思っていたが,第一巻を出版し残りの2巻も準備が整った後で,それが叶わないことを知った.彼は印刷屋への支払いをオーバーヘッドの特別予算から8万6,000ドル出費せざるを得ず,いつもは(機器研究所のことでは)寛大なMIT理事たちの眉をひそめさせた.工学部長は「彼は自分が正式手続きなしにかなりの額のお金を使ったことを認識し,後悔している」と述べた.結局のところドレーパーは資金を得て,航空工学には「機器工学」という古典が加わった.ドレーパーに言わせると,機器工学は学部レベルにおいてさえ「学部における航空工学教育の不可欠のものになった.空気力学,機体構造学,航空機エンジンと同じレベルで重要である.」
機器研究所で学んだ学生数の増大は,その教育界へのインパクトを測るひとつの物差しになる.研究所では1946年から1952年の間年平均20人が学位論文を書いた.1953年から1964年の間は年平均50人に上昇した.他に数百人が学期の間パートタイムで,夏の期間はフルタイムで働いた.1969年までには卒業生約800名を誇るに至る.研究所のスタッフは学科の数十の授業を担当し,複合履修の学生は年数百名を数えた.
ドレーパーは研究所を大学の学科というより会社のように運営した.それはむしろ昔の時代の工場に似ていた.後にシーマンスは「今でも私は廊下を歩き靴墨のにおいを嗅ぎ分けられると断言する」と冗談を言った.ドレーパーは実験室やオフィスをピカピカにすることには全く関心がなかった.「私は人生このかたずっと掃除道具入れの物置で暮らして来た」と彼はよく言った.彼は好んで緑のバイザーを被って実験室を歩き回り,ベテランの技師であれ新参の旋盤工であれ,いきなりきびしい質問を浴びせたり経験に基づいたアドバイスをしたりして驚かせた.見かけの破天荒な振る舞いの裏で,ドレーパーは真剣だった.当時のプログラム・マネージャーの一人のラルフ・レーガンは振り返る.「古代アテネの民主主義スタイルでは,管理の手際が良いと主人に文句を言うグループリーダーはほとんどいない.一方,今日ではマイクロマネージメントが今の流れだ.キー・テクノロジーは一日一日のベースで管理される.時には土日なしで,夜も昼も.」
研究所は射撃管制と慣性誘導の最新技術を軍だけでなく産業界にも広めた.1951年夏には研究所はIBMからの16名と空軍兵器研究所から派遣された3名の技術者のために12週のセミナーを開催した.「このセミナーの目的は,空軍用兵器の分野で合衆国空軍のための研究開発に携るこれらの人々を教育することにある」とその趣旨が述べられている. 1953年にはシーマンスが航空機会社と国の研究所からの86名のために自動制御の夏のセミナーを,ドレーパーは200名の産業界と政府機関の科学者,技術者のために航空機の射撃管制と飛行制御をテーマとした秋のシンポジウムを開いた.
戦時中にスペリーとの間で始まったパターンを継承して,研究所は数百人の企業のエンジニアを雇用し,複雑なテクノロジーの研究所から生産現場への着実な移転のために重要な実地での経験をさせた.ポラリス,タイタン,そしてアポロ計画の絶頂期に研究所には286人の企業エンジニアが常駐し,派遣した会社はACスパーク・プラグ(70人),レイセオン(51人),ベンディックス(72人),コールスマン・インスツルメント(20人),ハネウェル(10人)等である.1954年から1971年までの間に,ACスパーク・プラグのエンジニアは機器研究所に延べ9万1,662人・日の勤務実績を記録,同じ数字でベンディックスは4万2,908,ジェネラル・エレクトリック1万6,255,ハネウェル1万4,628,IBMは1万6,728,コールスマン1万6,792である.産業界に戻りたくなるように給料は低く抑えたとドレーパーは述べている.どのような理由にせよ,研究所は1946年から1970年の間に931人を産業界に送り出した.そのうち多くは,レイセオン,ハネウェル,GE,ベンディックス,そして他の直接契約企業である.
研究所とその卒業生とのより密接な結びつきを求めて,契約企業は関連部門の研究所を近隣に配置し,ドレーパーの卒業生を雇用した.ACスパーク・プラグは1959年に研究開発施設の支所をマサチューセッツ州ウェイクフィールドに設立し,ドレーパーの元部下の慣性誘導の専門家2名をその運営に当たらせた.1955年にマサチューセッツ州バーリントンにあるRCAの航空システム研究所(後のミサイル・エレクトロニクス及び制御部門)はシーマンスを引き抜き,後にこんどは彼が機器研究所の元スタッフ数人を招き入れた.ポラリス計画のための艦船用に小型化された慣性航法システムで機器研究所と共同研究していたノースロップのノートロニクス部門は,1959年にマサチューセッツ州ノーウッドに支部の施設を作り,研究所の技師を主任として雇った.ノートロニクス以外の全部はルート128と呼ばれることになる州道の沿線に集まった.
機器研究所の新卒者や熟練したスタッフも同様に産業界に積極的に採用されていった.ジェネラル・モーターズはボストンの新聞に1ページの全面広告を出し,新設したACスパーク・プラグ部門の開所を知らせ,「産業界の超有名企業と共に宇宙時代に踏み込もう・・・ジェネラル・モーターズ」と技術者たちを勧誘した.スペリーもこれに対抗してMITの立派な装丁の同窓会誌「テクノロジー・レビュー」に広告を打ち,SINSでの最近の仕事に触れて次のように言っている.「スペリーは,正確なナビゲーションデータを得るための海軍の先進電子システム,ジャイロシステムを開発中で,これは潜水艦を安定させ,その精確な位置,対地速度を常時把握し,標的のデータをミサイル誘導システムに自動的に送るという機能を持つものです.あなたがスペリーで取り組む仕事の内容はまさにそれです・・・スペリーを今すぐチェック!」
ドレーパーの起業家精神の影響は大きかった.1965年までに機器研究所からスピンオフして27の会社が生まれ,900人を雇用,合わせて1,400万ドルを売り上げた.それらのほとんど全てが慣性誘導技術の何らかの分野,すなわち解析,試験,製造(9社),回路・システム設計(8社),コンピュータ・ロジック回路設計(4社)を専門としている.ポラリスのために開発されたエレクトロニクス・モジュールを3社が商品化した.スピンオフのほとんどの会社は最初はコンサルティングで起業し,次いで製造業に移った.彼らもその母体である機器研究所と同様,ビジネスのほとんどを国防総省かその契約企業との間で行った.これらの企業は,最新の技術発展について行くために古巣の近くに居を構えた.それは機器研究所や空軍ケンブリッジ研究センターに近いケンブリッジの古い倉庫の中や,キャンパスから離れたリンカーン研究所やハンスコム飛行場に近いレキシントンやコンコードという地域であった.最も経営的に成功した一つであるダイナミクス・リサーチはその典型的なパターンを示している.空軍の誘導システム研究プログラムで働いていた2人のエンジニアが1955年に創立し,最初は慣性誘導・航法システムの解析を専門としていたが,後にこのシステムの部品や部分組立品の設計・製造に業務を拡大した.この過程で同社は数人のコンサルタント技術者から,レキシントンに本部を置き300人の社員と年商430万ドルの企業に成長した.1971年までに同社の技術スタッフ中の機器研究所の元メンバーは17人を数えたが,彼らが元の同僚らと接触した延べ時間は1,789人・日を記録している.
ドレーパーは,利益追求路線に進むことを一時は自ら考えていたこともあった.彼は1963年にエドワード・ボウルズとラルフ・レーガン(もと研究所の学生でレイセオンの誘導・再突入システム部門のマネージャー)に,会社内の独立した研究所の長として,あるいは機器研究所の一部を彼と一緒に会社に移行させるかして,レイセオンに移ることを真剣に相談している.しかし最終的には,高収入の魅力より大学の研究所が持つより大きな自由さの方を選んだ.
ドレーパーと彼の同僚たちは,彼らの学問的専門分野に軍の関心事と資金とがいかに大きく反映したかを決して否定しなかった.しかし1960年代の終わり頃までには,学部が軍との契約に圧倒的に依存していることと,それが研究と教育に及ぼす影響について,彼らのうち何人かが疑問を出すようになった.視察委員会は,事実上すべての学位論文研究が連邦政府(軍)との契約に依存していることを指摘し,「支援を得られない学位論文の分野もあり,今の研究所の状態は‘セックスアピール’に欠ける」と指摘した.学部の叩き上げのレオン・トリリングは,軍との契約研究の窮屈さや近視眼的なことを,また浮き沈みの激しい落ち着きのないパターン,外部から与えられる研究課題そのものを,あからさまに非難した.彼は同僚に「われわれがやっていることよりもっと別のこと,つまり航空機の高い性能よりもその経済性,信頼性,生産性,安全性のことをもっと考える」ことを主張した.そして民生向け技術の研究のために,防衛関連委託研究の間接経費を使って資金的「はずみ車」を設けることを提唱した.
ドレーパーも,研究所が民生技術への貢献を重視する必要があることを他人に劣らず感じていた.彼は,防衛研究プロジェクトが圧倒的だった唯一の理由は「研究所の能力を有効に使う軍事研究は長期的に安定した資金をもたらすが,そのような民生技術の資金は存在しない」ためだと説明した.それ自体軍事技術の副産物だが,アポロのナビゲーションシステム以外は民生技術分野からの支援が実現したためしはない.
ジェローム・ハンセイカーも同じように予想していた.— MIT航空工学の最初の専任講師として,その最初の博士号候補生として,また創立時の(そして長年の)学部長として — 30年にわたって彼は高まる軍の関心とその結果とに憂慮を募らせて来た.彼は1948年に研究教育推進室のために学部の研究・教育の歴史の概要をまとめたが,それはMIT航空工学に蔓延する軍の影響について同僚の目を開かせることになったかも知れない.自分が海軍士官として1914年に授業を開講したこと,後継者を1926年に海軍航空技術研究所の次官補として雇ったこと,多くの陸軍,海軍,空軍の士官が研究・教育プログラムに派遣され専門的教育を受けたこと,軍のために行われた実験や研究の数々,そして軍関係の機関に就職した卒業生の割合,これらすべてを見て,彼は最終的に次のような結論に至った.「おそらく軍事目的ではない航空機産業が構想されるべきだろう.過去においてはあり得なかった.直近の未来もまたあり得ない.しかし遠い将来におけるそのような産業に向けての研究は最大限の財政支援に値するものだ」.ハンセイカーは3年後に学科長を辞めたが,そのような将来の姿を見ることなく死んだ.彼の後継者は全く違った未来を思い描いた.そしてハンセイカーの夢はさらに遥かに遠くに行った.
2017-02-05 00:17
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(3)



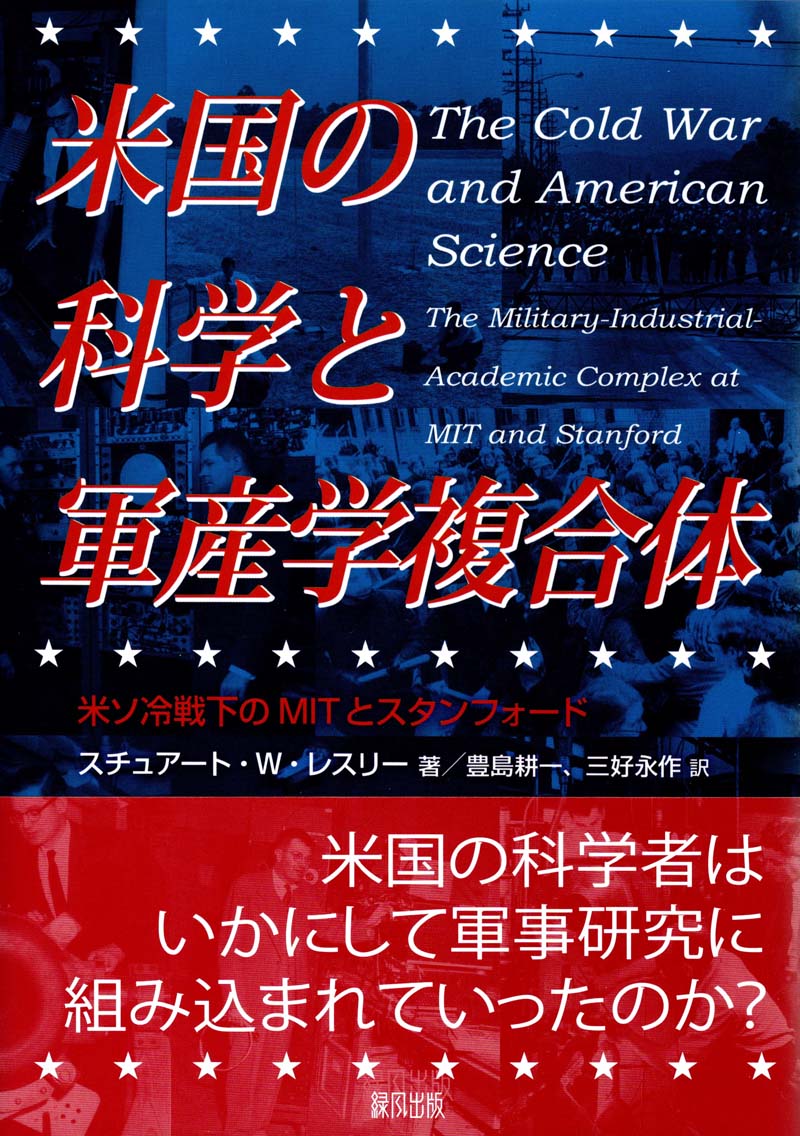


 9条守ろう! ブロガーズ・リンク
9条守ろう! ブロガーズ・リンク



コメント 0